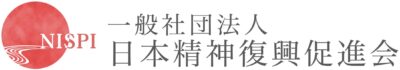2025年8月13日
戦後80年、「日本精神」は再び目覚めるのか/第2回 私たちは何を忘れたのか――日本精神の空白と復元の兆し
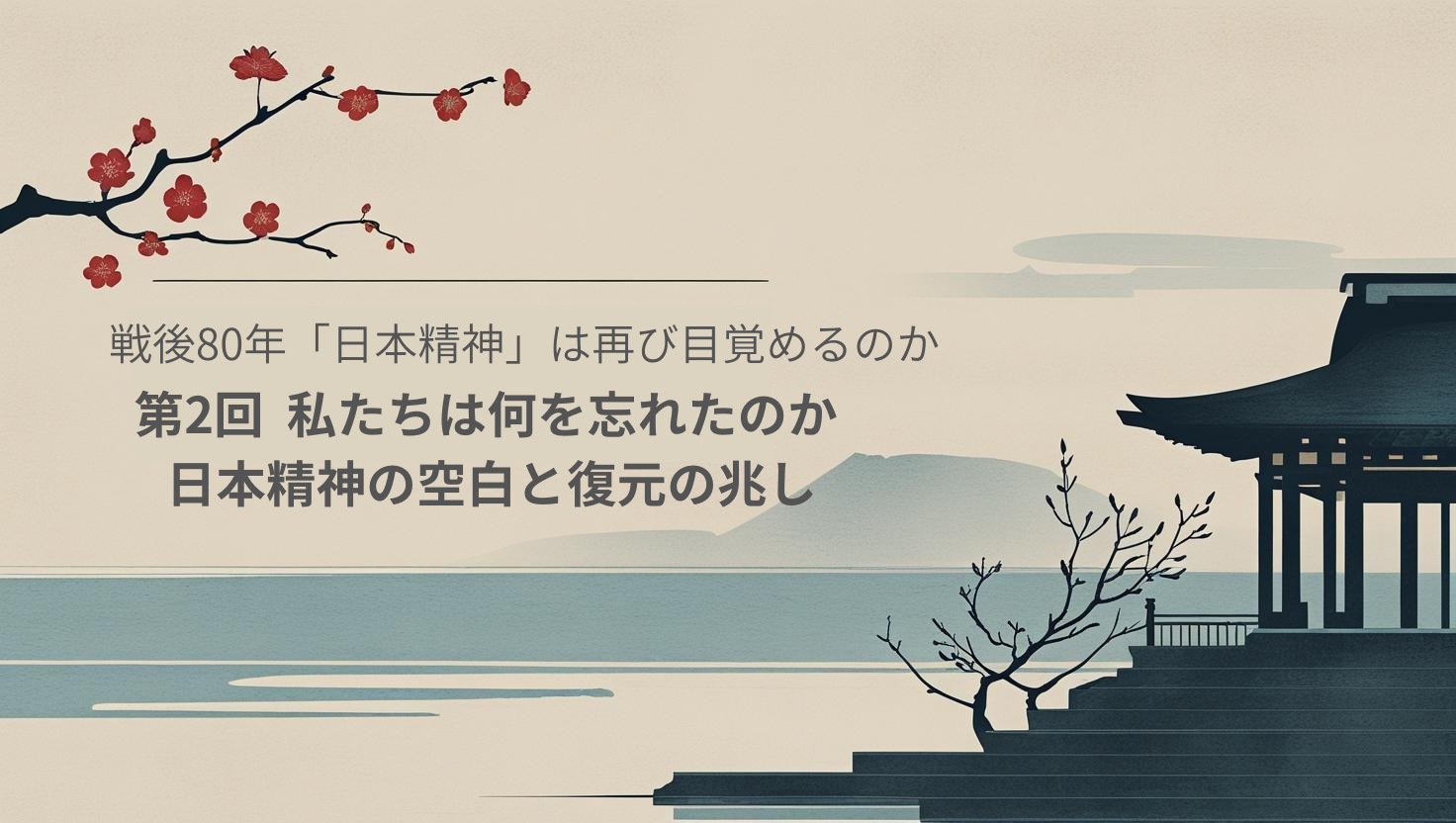
かつての「日本らしさ」
戦前の日本社会では、「秩序を守る」「恥を知る」「他者を思いやる」といった価値観が、家庭や地域の中に自然に息づいていた。
子どもは祖父母から家系の話を聞き、年中行事を通して祖先や自然への敬意を学んだ。こうした“無言の教育”は、教科書や制度以上に、精神の根幹を支えていたのである。
しかし、戦後の教育制度や家庭観の変化により、それらは徐々に姿を消していった。
精神的な空白が生んだ“無関心”
戦後世代が社会の中心を担うようになると、「祖先との断絶」「地域との断絶」「国家との断絶」が当たり前になっていった。
家系や地域の歴史を知らず、祝祭日や神事にも無関心。さらには、政治や社会に対しても「誰かがやってくれるだろう」という受け身の姿勢が広がった。
これは個人の性格の問題ではない。価値観を語る場を奪われた社会が、生み出した“空白の精神状態”である。
それでも残った“日本人らしさ”
それでも、日本人の内には根強く残っているものがある。
災害時に見られる秩序正しさ。ボランティア活動への自発的な参加。言葉にしない空気を読む力。これらは、失われたはずの価値観の“残像”である。
Z世代の中には、祖父母の話に興味を持ち、神社仏閣を訪れる若者も増えている。SNSでの家系図ブームや“家訓”への関心も、精神的ルーツを探そうとする動きの表れだろう。
「復元の兆し」をどう育てるか
こうした兆しは、国家的なプロジェクトからではなく、家庭、学校、地域といった“身近な場”から育っていく。
伝統行事を見直す。家族の歴史を語る。郷土の文化を知る。そうした小さな営みが、精神文化の復元につながっていくのだ。
【第3回への予告】
次回は、こうした復元の動きを“具体的な実践”へとつなげていく方法を探る。皇室を中心とした文化的伝統や「和の秩序」が、現代社会にどう活かされるのか――。
NISPIの示す道筋から「これからの日本精神再建の道」を見つめたい。